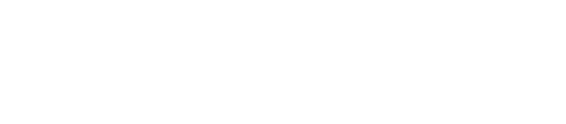基本的な考え方
事業ポートフォリオ変革を進める上で、事業戦略の実現と利益創出、更には事業活動を通じた社会貢献を達成するために、「全ての従業員が変化を楽しみ、高い目標に果敢に挑む」状態となること、つまり、組織エンゲージメントとワークエンゲージメントの両方が高い状態にあることが必要だと考えています。これらを実現するために、社員との関わりを大切にし、一人ひとりの個性や強みを尊重した取り組みを行っています。
推進体制
日清紡ホールディングス(株)は、2025年4月に、スピード感をもって変革をリードし統括する体制の構築を目的として、各機能別組織に担当執行役員を置く組織再編を行いました。人財・D&I推進室を設置し、配下に3つのグループ(人財開発グループ、D&I推進グループ、人事総務グループ)を配置しました。毎月の人事責任者会議(HRO会議)に加え、年2回、全国内グループ会社の人事担当者の集う会議(グループ人事方針会議、グループ人事戦略会議)を開催し、横断的に人事関連の方針・課題について討議しています。
当社グループの最高責任者である当社社長は、毎年経営戦略会議※ においてマネジメントレビューを実施し、人財・D&I推進室担当執行役員による当社グループの取り組みと進捗などの状況報告を受けて、経営上必要な実施事項を指示しています。特記事項などについては適時取締役会に報告されています。
※ 経営戦略会議:取締役および監査役・執行役員により構成される業務執行会議
当社のサステナビリティを推進する組織体制の概要については、「サステナビリティ推進体制」をご覧ください。
日清紡グループの具体的な取り組み
第5期サステナビリティ推進計画(達成年度2024年度)
2024年度を達成年度とする「第5期サステナビリティ推進計画」では、エンゲージメントと、グループ企業理念の実践を重点活動項目とし、「グローバルサーベイの実施」と「グループ企業理念に基づく経営者メッセージの発信」を達成するために、以下2項目を目標・KPI※ として定めて活動しました。
※ KPI:Key Performance Indicator 業績管理指標・業績評価指標
- ①グローバルサーベイの継続実施
- ②グループ企業理念・VALUE・行動指針の実践推進(グローバルサーベイでの肯定率 80%以上)
①については企業理念を浸透させる組織の状態を可視化する取り組みを行いました。グローバルサーベイを2024年度まで継続して実施し、その結果をもとに各社毎の組織風土改善活動に活用しています。②グループ企業理念・VALUE・行動指針の実践推進(グローバルサーベイでの肯定率 80%以上)を目標として活動を進めた結果、グローバルサーベイでの肯定率は国内外を含めたグループ全体で2024年度77%となり、2023年度の結果76%より若干ながら改善が見られました。
第6期サステナビリティ推進計画(達成年度2027年度)
2027年度を達成年度とする「第6期サステナビリティ推進計画」では、エンゲージメントとグループ企業理念の実践を重点活動項目とすることを継続し、「グローバルサーベイの実施」と「グループ企業理念に基づく経営者メッセージの発信」を達成するために、以下2項目を目標に掲げ、引き続き活動を進めていきます。
- ①グローバルサーベイにおけるエンゲージメントスコア80%以上
- ②グループ企業理念・VALUE・行動指針の実践推進(グローバルサーベイでの肯定率 80%以上)
企業理念の実践・推進に向けた研修資料の展開などを行いながら目標の達成に努めていきます。
サステナビリティ推進計画の概要については「サステナビリティ推進計画とKPI」をご覧ください。
グループ企業理念の実践
「第5期サステナビリティ推進計画」では「グループ企業理念の実践」を重点活動項目として設定し、「グループ企業理念に基づく経営者メッセージの発信」を取り組み事項として「グループ企業理念・VALUE・行動指針の実践推進(グローバルサーベイでの肯定率 80%以上)」というKPIを設定して活動しました。
企業理念を浸透させるため、グループ各社の社長からさまざまな機会を通じてメッセージを出すなどの取り組みに加え、企業理念ハンドブックの多言語化の充実、ラーニングマネジメントシステムを活用した教育動画の配信などの取り組みを行いました。
教育動画は、毎年内容を変えながら配信しています。2024年度はグループ企業理念にある「挑戦と変革」にスポットを当てました。事業の競争環境などが目まぐるしく変化する現在において、前例踏襲の考え方では現状維持すら困難な時代になってきています。企業理念の実現に向けて、2024年2月に公表した中期経営計画では、「つなげる技術で価値を創る」という姿を目指し、センシング・無線通信・情報処理技術で社会課題へのソリューションを提供していくという当社グループの「挑戦と変革」の姿勢を表明したことを受けて、事業内容やビジネスモデルを変えて高収益化を実現していくために、各従業員の変化対応力を高めるヒントとなるような内容を盛り込んだ教育としました。
第5期サステナビリティ推進計画の最終年度として2024年度のKPIの結果は、海外子会社も含めた全グループでグローバルサーベイでの肯定率は国内外を含めたグループ全体で77%となり、第6期のサステナビリティ推進計画でも継続課題として取り組みます。サーベイの結果分析・理解促進を進め「挑戦と変革」を加速していきます。
エンゲージメント向上施策 ~グループ従業員サーベイの実施~
グローバル市場を見据えた競争力を維持するために、グループ全体のエンゲージメントスコアを80%以上にすることをKPIとして設定しました。2024年は国内全グループ会社(38社)、海外43社、計81社(88%)が参加、参加者は20,772名、回答率は96%といった、グローバルな調査においても非常に高い回答率でした。エンゲージメントスコアはグループ全体で72%、海外は88%、国内は64%という結果でした。
組織エンゲージメント向上に資する取り組み
各社のトップとメンバーが一体となって取り組むため、各社にはサーベイ担当者を配置し、取り組み事例をグループ全体で共有しています。さらに、2022年より開始した心理的安全性に関する教育を継続的に実施し、全社員に共通の認識を浸透させていきます。また、2025年度には、ホールディングス主導で経営層や管理職層に対する施策を実施したいと考えています。
ワークエンゲージメント向上に資する取り組み
自己成長やスキルアップを促進するための各種研修制度や教育ツールの提供、キャリアの棚卸しの機会(年代別キャリア研修やキャリアシートの記入・キャリア面談の実施)、適切なフィードバックの実施など、社員一人ひとりの成長を支援しています。さらに、人事ポリシーに基づいた人事制度や報酬制度の整備も行っています。
組織エンゲージメントとワークエンゲージメントのベースとなる環境整備
フレックスタイム制やテレワーク勤務といった柔軟な働き方の導入、また健康増進策として健康展の実施や、女性向けの健康関連教育を実施するなど、持続可能な環境づくりを進めています。
労働組合の結社状況(国内外)
国内外のグループ会社において、各国・地域の法令などに基づいて、各社の労働組合や従業員代表と従業員の労働条件や各社の経営状況に関して定期的に対話を行い、相互信頼的な労使関係を維持しています。日清紡ホールディングス(株)では、国内外のグループ会社における労使関係の状況を把握しており、必要に応じてグループ会社へのサポートを実施しています。
国内グループ会社の労働組合は、UAゼンセン同盟や電機連合に加盟しています。いずれも良好な労使関係を築いており、毎年労使協議会のほか、労使の懇談の場を設けるなど健全な状態にあります。労働組合と締結している労働協約の中で、業務上の都合により従業員を異動や配置転換するときは、対象者本人の意向を考慮することを定めており、決定後は速やかに労働組合にも連絡しています。事業再構築に伴う配置転換などが生じた場合については、雇用の確保を基本として労働組合と協議をしています。
従業員の安全衛生に関しては、安全確保と健康の保持増進、快適な作業環境の形成を促進するため、グループ安全衛生連絡会議の開催や安全監査を実施するなど、労使が一体となり、国内外のグループ会社における安全衛生のレベル向上に努めています。
グループ会社社員と経営トップとの対話
日清紡グループについてより理解を深めてもらうため、日清紡ホールディングス(株) 社長がグループ会社を訪問し、社員と直接対話するミーティングを2021年から実施しています。
これまでに海外事業所を含めた45拠点で行われ、およそ2,000人の社員が参加しました。1回のミーティングの参加人数を15人程度の少人数に絞り、質疑や意見交換に多くの時間を割くようにして、社員一人ひとりが社長とより深いコミュニケーションを取れるようにしています。現場で働く社員からは、今後の当社グループについて、サステナビリティ、D&I、DXへの取り組みといった幅広い質問が寄せられ、対話を通じて活発な意見交換が行われています。
2024年度は新たに(株)国際電気が当社グループの一員となり、各拠点を訪問してミーティングを実施しました。社長からは当社グループ全体の現況や無線・通信セグメントのさらなる成長に向けての期待について語られています。

従業員持株会
2024年より、国内グループ全社で従業員持株会制度を導入できるようにしました。2024年12月末時点の加入会社は20社となり、対象会社の加入率は約54%です。
日清紡グループ従業員持株会は、従業員が自社の株式を取得・保有することについて、会社が便宜を図り、援助してこれを奨励する制度です。従業員から一定金額を拠出してもらい、自社株式を共同で購入、拠出額に応じて持分を配分します。従業員持株会への加入を通じ、従業員の資産形成の一助とするほか、経営への参画意識を高めて担当業務へのモチベーションアップにつなげています。
グループ会社における活動事例
労使懇談会
ジェイ・アール・シーエンジニアリング(株)では、2カ月に一度、労使懇談会を開催しています。経営側と労働側の代表者が集まり、会社の経営状況、労働条件、福利厚生など、労使双方に関わる重要な事項について意見交換を行います。
人事制度の改定、賃金制度の改定、労働環境や職場環境、安全衛生に関する取り組みなど、具体的なテーマが議論されることが多いです。直近では、嘱託人事制度に関して約1年かけ経営と従業員代表とで話し合い続けた結果、制度を制定する事ができました。
労使懇談会は、従業員代表が従業員の意見を経営に反映させるための重要な機会であり、労使間の信頼関係を構築し、より良い職場環境を作る上で不可欠な役割を果たします。経営側としても問題の早期発見や未然防止にもつながると考えています。
タウンホールミーティング開催
(株)五洋電子では、経営トップと社員一人ひとりとの、より深いコミュニケーション機会を提供し、経営方針および会社状況への理解・浸透を図ることを目的として、社長と社員が直接対話をするタウンホールミーティングを実施しました。
2024年度は各部署から選抜された社員計7名が参加し、テーマには経営方針や3カ年計画の内容を主眼として、社員からの質問に社長自らが答え、活発な意見交換の場となりました。
普段会話をする機会の少ない社長のメッセージを直接受け取り、対話を通して業務における問題の本質を考える良い機会となり、大変有意義な時間を作ることができました。
同社では、今後も定期的にタウンホールミーティングを実施し、経営トップと社員とのコミュニケーションを深めていきます。

「HR clinic project」 社内コミュニケーション向上のための重点活動
タイのNisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd.では、社内コミュニケーションをさらに向上させることを目的とした「HR clinic project」の運用を開始しました。
プロジェクト活動として、社員に関わる規定・福利厚生・税金・法律に関する知識を高める取り組みを行いました。人事課を中心に、食堂や休憩室にて相談コーナーの設置やQ&A大会の開催を行い、各事務室へ「HR Clinic Patrol」を実施しました。また、社員にPR活動も行いました。
12ヶ月間実施した活動について、社員からは、「活動をとおして知識を得ることができ、とても良い機会だった」、「うまくコミュニケーションが取れるようになった」、「今後もこのような活動を継続して欲しい」と好評でした。
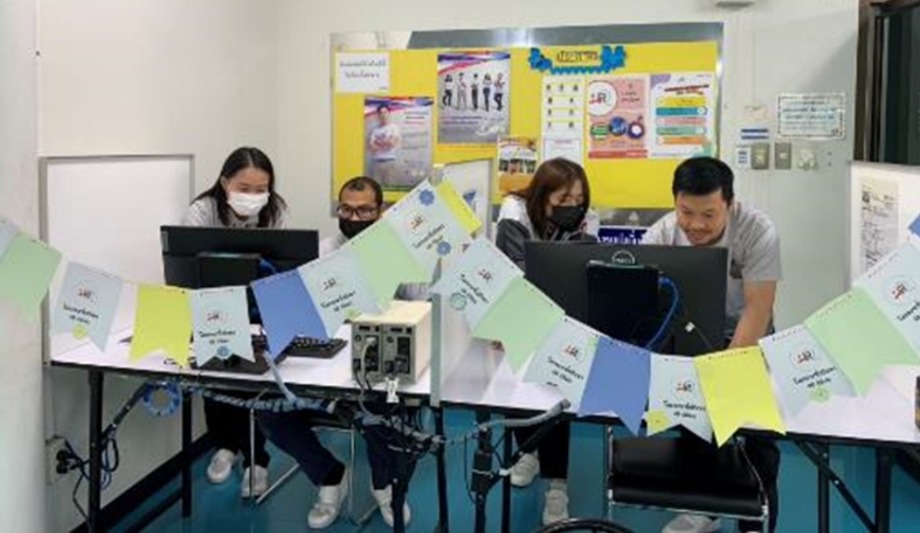
職場におけるオープン・ドア・ポリシーの運用
アメリカのNisshinbo Automotive Manufacturing Inc.では、従業員が関心や懸念のある事項について、直属の上司やマネージャー、人事担当者に相談できる体制を構築し、社内に広く周知するためのオープン・ドア・ポリシーを運用しています。この制度は従業員の利益のために利用できるよう確立されています。従業員がもつ不安要素・課題には、勤務時間や労働条件、制度に基づく権利、給与、不公平または不平等な扱いや懲戒、あるいはハラスメントなどがあります。
このオープン・ドア・ポリシーは、従業員からの意見等を真摯に受け止めつつ、会社の考えも伝えながら、公正かつ迅速に問題を解決することに役立っています。この制度は、従業員の立場を守り、守秘義務に基づき、適切に運用しています。
また、従業員がお互いを尊重し、人権意識を高められるように、研修などを通じてその風土を醸成するよう努めています。
情報の共有・コミュニケーション促進
日清紡メカトロニクス(株)では、経営層と従業員とのコミュニケーションを促進すべく、様々な機会を設定しています。半期に一度、経営トップ自らによる、経営スローガンや会社業績などを、全従業員に向け説明する場を設けています。また、当日は会社トピックスについて、対象業務に携わる若手社員が発表を行い、自他ともに啓発する教育の機会としています。この内容は、同社の海外拠点に対してもeラーニングシステムにて配信しています。
また、四半期に一度、部課長をはじめ係長層が出席し、各部門の業績やトピックス、連絡事項などの共有を行っています。諸規則・諸規定の改定点や関係法令の変更に伴う対応、各種教育の機会にも活用しています。
そのほか、部門別に座談会やタウンホールミーティングを開催し、それぞれの部門内における情報共有も進めています。これらの機会を通じて、会社の状況やトピックスの共有を進め、相互の意思疎通を推進しています。

2025年度 南部化成経営方針発表会を開催
南部化成(株)は、2025年1月「2025年度南部化成経営方針発表会」を開催しました。発表会には、来賓の皆さまならびに同社の役員および社員約300名が出席し、来賓挨拶に続いて、社長および南部化成グループ各社を含めた各拠点長からの方針発表後、入社25年の方の永年勤続表彰や、2024年度の最優秀拠点賞などの各種表彰などを執り行いました。
発表会の終了後は、静岡市内のホテルに会場を移して懇親会を開催し、各種の料理や飲み物を片手に、ビンゴゲームなどでそれぞれ思い思いに交流を深めました。
同社では、2025年度のグループスローガンを「事業変革を加速し、利益を創出する」として、従業員一同で各種の取り組みを進めていきます。
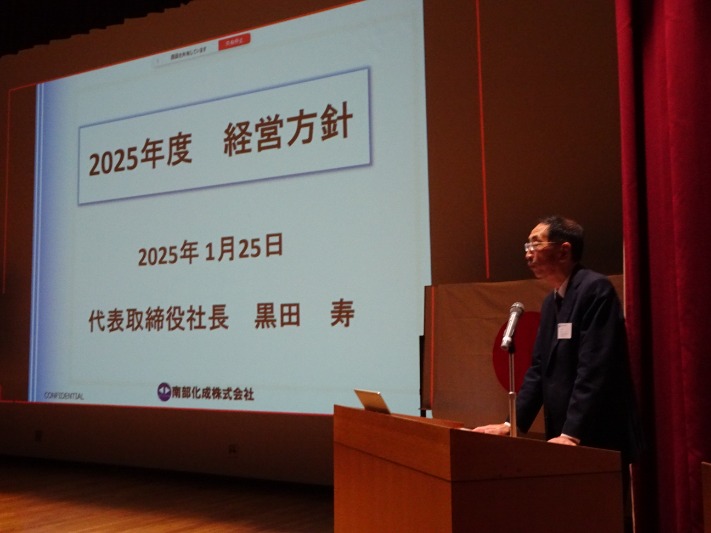
従業員満足度調査の取り組み
フィリピンのToms Manufacturing Corporationでは、四半期ごとに従業員満足度調査を実施しています。会社に対する従業員の満足度を把握し、改善につなげることを目的としています。また、同調査は、従業員が会社の運営状況や会社に対して好意的な意見を持っているかどうかを経営陣が判断するのにも役立ちます。
調査項目は、ワークライフバランス・仕事に対する姿勢・能力開発・チームワーク・職場環境・仕事のやりがい・人権問題・ハラスメント・労働安全衛生・ジェンダーレスなど多岐に渡ります。会社に対する改善要望を自由に記載する項目もあり、頂いた貴重な意見や改善要望については幹部会議で議論し改善につなげています。従業員は、当該満足度調査実施について、自分の意見や要望を伝えられる機会として概ね好意的に捉えています。今後も組織風土改善の取り組みとして継続していきます。
組織風土改革
日清紡テキスタイル(株)では、組織風土改革に取り組むため、第一段階として「従業員の意見を聞く!!」ことを目的に、各事業所に沿った形式で意見収集を実施しました。
本社・大阪支社では、役職問わず事前に「意見カード」を2枚/人配布し、ヒアリング会(4~5名/回)の際に「意見カード」を記入しました。意見が記入されたカードを参加者が分類・仕分けることにより、意見の追加や参加者同士の意見交換にもつながりました。集まった意見は集約し、個人が特定されないよう配慮の上、参加者へ情報の提供を行いました。
各事業所から計250件を超える会社、職場、働く環境などのさまざま意見が集まりました。従業員からの意見・提案を元に、2025年度に同社の組織風土改革を実行していきます。
若手幹部との面談
ブラジルのNisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA.では、若手幹部および幹部候補と工場長が半年に一度のペースで定期的に面談を行っています。
工場長はこの機会を通じて、普段直接話をする機会が少ない若手幹部へ会社方針や他部署での取り組み、工場全体での課題などについて説明をしています。若手幹部からは自身が取り組んでいることや、やりたいこと、問題点などをざっくばらんに話してもらっています。若手幹部からの意見は、ベテラン幹部へと展開し、前向きに検討したり、即実行に移せるものは実践しています。
この取り組みが改善活動へもつながっています。若手幹部からは「自分の意見を直接伝えることができる」、「会社が行っていることがよく理解できる」、「継続してほしい」という声が上がっており好評です。
同社は、より良い会社とするために、若手、ベテラン問わず自分の意見を自由に出せる環境づくりを行っています。

Nisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA.創業50周年式典開催
ブラジルのNisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA.はサンパウロ市内に本社を置き、約170km離れたイタぺチニンガ市に工場を構えて、1974年11月に創業を開始し、2024年には創業50周年を迎えました。創業50周年を記念して、日本から日清紡ホールディングス(株)の社長と、日清紡テキスタイル(株)の取締役が来訪し、同社の工場があるイタペチニンガ市で2つの記念式典を開催しました。
1つは、連邦議員やイタペチニンガ市長を始め多くの行政関係者、またそのOBの方々など、約200名が参加した記念式典です。この式典では、同社の発展をともに祝い、沢山の方からご祝辞を頂き、同社の50周年記念ビデオの上映や、和太鼓演舞などがあり大盛況でした。
もう1つは、同社の従業員約450人とその家族を合わせた総勢約1,000名が参加したパーティです。シュラスコ(バーベキュー)やビンゴ大会に加え、プリクラマシーン、子ども向け遊具も設置して盛大な式典となりました。

全社員対象の個別面談
日清紡都市開発(株)では、社長が毎年、全社員を対象に個別面談を行っています。この面談は、対話を通じてスローガンの浸透、会社の方向性や日常業務とのつながり、問題の本質、自己研鑽などについて考える機会を提供しています。
従業員からは、上から目線ではなく対等な姿勢で対話してくれた、経営ビジョンや今後の戦略について説明を受け納得感が得られた、努力や成果を認めてもらえモチベーションが上がった、キャリアアップの道筋や具体的目標について示唆を受けたなどの反応がありました。
社員の声を直接聞くことができる場として、また社員が自らの思いを直接伝えることができる場として、非常に重要な取り組みであると考えています。今後も継続的に実施し、より良い組織づくりやコミュニケーションの向上を図りたいと思います。