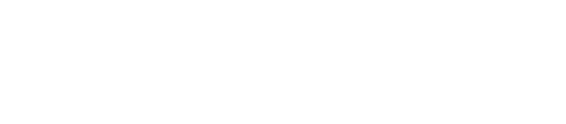トップメッセージ

社長就任にあたって
本年3月に代表取締役社長に就任した石井靖二と申します。
私は、1988年に日清紡績(株)に入社して以来、ブレーキの摩擦材をはじめとする生産技術畑を歩んできました。その過程では、海外での工場新設・増設などにも携わり、製造部長やブレーキ事業全般を統括するマネジメント業務も行ってきました。
生産技術を軸としながらも、毎年のように新たな仕事を手掛け、またそこから多くを学び、都度、達成感を得られたことは、私にとっては喜び も大きく、働きがいもありました。しかし同時に、グローバルで事業環境 が急速に変化を続ける中、事業や産業の栄枯盛衰とそれに対応してポー トフォリオ変革に挑む日清紡グループの成長性について、客観的かつ論 理的な視点で、さまざまな思いや考えを巡らせてきたのも事実です。
日清紡グループは、2009年に繊維・ブレーキ・紙製品・精密機器・化学 品の5事業を分社化、ホールディング制への移行を行い、無線・通信事業 とマイクロデバイス事業を中心とするエレクトロニクス分野を成長エン ジンとする方向へと事業ポートフォリオの入れ替えを進めてきました。 この16年の軌跡を振り返るだけでも、非常にドラスチックな変化を遂げ てきたことは実績としてお示しできています。
しかし、足元の業績は低迷を続けており、その成長力について、私は強 い危機感を抱いています。
社長に就任するにあたって私は、社員に向けて「危機を力に、挑戦を成 長に――未来への軌跡を共に築く」という新社長ビジョンを共有しました。 傷んだ財務基盤について全社でしっかりと認識した上で、この危機をバ ネに変えていくためには、財務体制だけでなく、事業やビジネスモデル そのものの変革も求められます。
『論語』に、難しいことを成し遂げるには、よこしまな思いがあっては ならないという「思無邪(しむじゃ)」という言葉があります。この言葉を 胸に、現状からどのように変化させていくのか、まずは経営が「挑戦と変 革の具現化」についての設計図を描き、それに沿って事業ポートフォリ オ変革などの大改造を推し進めていきます。業績の回復は喫緊の課題と 認識しており、このビジョンの下で見えてきた動きや成果についても、 わかりやすくお示しすることを意識して、経営を行っていきます。
日清紡ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石井 靖二

■PROFILE
| 1988年4月 | 当社入社 |
| 2011年4月 | 日清紡ブレーキ㈱執行役員 摩擦材製造部長 |
| 2013年4月 | 同社常務執行役員 戦略室長、生産部門長(兼務)、生産技術部長(兼務) |
| 2013年6月 | 同社取締役 常務執行役員 |
| 2015年1月 | 同社ブレーキ開発部長 |
| 2015年4月 | 同社取締役副社長 |
| 2015年6月 | 当社執行役員 |
| 2017年6月 | 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 |
| 2019年3月 | 当社取締役 執行役員 |
| 2023年3月 | 日清紡ブレーキ㈱取締役会長 当社経営戦略センター副センター長 |
| 2024年3月 | 当社取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 |
| 2025年3月 | 当社代表取締役社長(現職) |
2024年度業績の評価
売上高は前期にブレーキ事業の子会社を売却したことな どから減収となり、営業利益については、国際電気グルー プの連結子会社化の影響から増益となりました。当期純利 益も増益となりましたが、前期に計上したブレーキ事業子 会社の売却に伴う特別損失がなくなったことで黒字化を果 たしたものであり、内容的には非常に厳しい結果だったと 私は受け止めています。毎年、外部環境の変化などによる 影響で業績は多少変動しますが、単年だけでなくここ数年、 目標未達で厳しい業績が続き、市場からの期待を裏切り続 けてしまっていることには強い危機感を抱いています。な かでも注力している無線・通信事業の業績は、(株)国際電気 の連結子会社化で大幅な増収増益にはなったものの、営業 利益は計画を下回っており、大いに反省すべき要素がある と認識しています。
私は業績回復を大命題として、まずは無線・通信事業の構 造改革を加速していきます。そして、市場動向や産業全体 の視点から今後の成長が期待できない事業については、メ リハリをつけてこの先の方針を決めていく予定です。
中期経営計画2026
また、2024年度は「中期経営計画2026」の初年度でした。 中計では「事業ポートフォリオ変革の追求」「将来の成長に 向けたビジネスモデル構築と経営資源の重点投入」「経営基 盤のさらなる強化による経営リスクの低減」を重点施策に掲 げ、2026年度に売上高5,800億円、営業利益380億円、連結 ROIC6%、連結ROE10%の数値目標を掲げています。
この中期経営計画の方向性や数値目標について、現時点 では大きく変えませんが、当初の前提条件を変えていくよ うな方針を決定した際には、適宜その内容を公表していき ます。
事業ポートフォリオ変革の追求
重点施策である「事業ポートフォリオ変革の追求」に関 しては、引き続き無線・通信事業に注力し、構造改革を加速 していきます。2023年に買収した(株)国際電気に関して は、(株)国際電気と日本無線(株)のマネジメントを巻き込 む形で、1年以上かけて当事業の事業戦略を練ってきており、 PMI(Post Merger Integration) は順調に推移しています。 スムーズなPMI には初動が非常に重要ですから、(株)国 際電気のM&A に関しても最初から私自らが(株)国際電気 に出向き、当社の内情などをすべてオープンに話し、経営陣 やスタッフとの間に信頼関係を築いてきました。
無線・通信事業は官公需と民需とに大別できますが、(株) 国際電気と日本無線(株)との技術面での相互補完的なシナジー効果を創出することで、岩盤事業としての官公需事業をより強化すると同時に、成長事業としての民需事業をよ り伸ばしていきます。事業体制と生産体制を効率化する構 造改革を通じて、強靭な経営基盤を実現しながら、両社の強 みを活かした無線通信インフラのプラットフォーム化など の投資を通じて、官公需事業だけでなく民需事業の成長に も挑戦していきます。
マイクロデバイス事業は、2024年度の業績からも、抜本 的な見直しが急務と認識しています。半導体産業は業界構 造として、大きな在庫サイクルがあり、市況の変動に左右さ れやすいビジネスモデルだと言われています。しかし、今 の半導体産業をグローバルで俯瞰すると、例えば、中国企 業が技術・設備の面でトップ集団に肉薄しつつあるなど、こ れまでのビジネスセオリーが崩れかねない不安定要素も確 認できます。「半導体」と一言で括ってもその中身は幅広く、 その中で日清紡グループが注力するマイクロデバイスの位 置づけから、ビジネスポートフォリオの見直しを図ってい く必要があると考えます。
マテリアル事業の中で、私が長く従事してきたブレーキ事業については、欧州子会社のカーブアウトが完了し、今後 の構想はすでにあります。一方、ブレーキ以外の事業につい ては、事業ポートフォリオ変革を加速すべく、各産業のビジ ネスセオリーや市場性を踏まえた上で、2025年から方向性 を機関決定しながら活動していく方針です。すべての産業 には栄枯盛衰があります。一方で、納得感が得られないと人 の行動には結びつきません。ですから経営陣だけでなく従 業員にも、各事業で期待できる将来的な成長力や社会貢献 を調べ、考えてもらい、方針決定へと進めていく考えです。
将来の成長に向けたビジネスモデル構築と 経営資源の重点投入
経営資源については、エレクトロニクス領域への積極投 資を継続します。中期経営計画では、M&A 等を含めた戦略 投資を累計で約400億円予定しています。すでに無線をコ ア技術としたローカル5G などへの投資が進んでおり、特に 国土の広い米国市場へのアプローチや人的投資も実行しています。また5G の最大の特長は、データをリアルタイムで提供できることにあり、そうしたデータと日清紡グルー プの考えるDX ともいえる事業のスマート化とを組み合わ せることで、具体的なサービスにもつなげていきます。 一方で、今後の投資の大部分は、今回発表した新たな研 究体制下での研究開発投資になります。2025年4月1日付 けで、既存の研究組織を整理・統合し、新たにフューチャー イノベーション本部を新設しました。その目的は、これま での技術R&D から事業R&D への転換を図ることです。
これまで、研究開発は主として中央研究所がプロダクト アウト型(技術R&D)で進めてきました。しかし、これから の時代を見据えるとその形では限界があり、モノからコト へと需要がシフトする中で、よりマーケティング寄りの事 業R&D を推し進めながら、AI やソフトウェアを活用してさ まざまな通信手段を一つに束ねたプラットフォーム化に注 力することが重要と考えます。
例えば、官公需事業では、自然災害が激甚化する中で、AI を活用しながら水・河川の動向をいち早く情報提供するビ ジネスへと発展させるなど、既存事業での競争優位性を強 めながら、デジタル技術やAI を活用して、モノとサービス への取り組みにつなげていく体制を構築していきます。
私は技術畑出身として、自らこのR&D 体制にコミットし、 研究者とともに新たなビジネスモデルの早期構築に注力し ていきます。研究開発の人員体制についても、純粋な技術 の研究者に加え、ソフトやAI、さらにはマーケットを研究 する部隊が相互に情報交換していける体制とし、機動性の 向上を図ります。新研究体制については中計の策定時には 織り込んでおらず、その具体的な中身については具体例と ともに今年中にはお示ししていく方針です。
ホールディングスのガバナンスにおいては、これまでの 経営戦略センター長をトップとするピラミッド型の組織体 制から、各執行役員に決裁権限を与え、当社が進めるべき事 項を迅速な意思決定を通じて同時進行で進められる体制に していきます。
経営基盤のさらなる強化による 経営リスクの低減
重点施策の3つ目の経営基盤は、サステナビリティ経営に 関わる部分です。環境配慮やSDGs への貢献は、企業として 当たり前に行わなければならないことと認識しています。
一方、これまで海外の方々と仕事をする機会が多かった 私にとって、サステナビリティ経営の中で最も複雑かつ重 要だと捉えているのが人権の尊重です。これにはD&I の推 進や各種ハラスメントの撲滅も、当然含まれます。一度踏み にじられ傷つけられた人間の心は、簡単に元に戻ることは ありません。倫理通報制度といったシステムの整備も重要 ですが、それ以上に重要なことはやはり教育です。グローバ ル企業として、各国の国情や歴史認識といった人権の背景 にあるものを踏まえた上で、マネジメントが自ら率先垂範 して人権を尊重した行動姿勢を示さなければなりません。
環境に関しては、2050年のカーボンニュートラル達成に 向けて、道のりは決して平坦ではないものの、必達命題と捉 えた上で、電力の契約形態における工夫や、場合によっては 工場の移転も辞さないなど、ありとあらゆる手を尽くして 検討し達成を目指します。
同時に、燃料電池部品などのGHG(温室効果ガス)削減に 資する技術開発への注力や、得意とするアナログ半導体の 分野での消費エネルギー節減に向けた研究、さらには環境 に貢献する製品の開発にも力を入れていきます。EMS(電子 機器製造受託)事業強化でスマート化を進めることも、環境・ 社会貢献につながると考えます。
また、製品自体の研究開発も進めながら、水使用量の削減 にも引き続き地道に取り組んでいきます。
人財に関しては、多様な考え方を持った人財を活かすこ とがイノベーションにつながります。特に事業ポートフォ リオ変革を推進していく上での最重要課題は人財です。未 来を創る上で欠かせないソフトウェアエンジニアとAI エン ジニアの確保は喫緊課題であり、日本人だけでなく、米国や インドなどの海外人財の活用も視野に、ジョブ型人事制度 の導入など、人財活用戦略をグローバルで推し進めていき ます。
同時に、コミュニケーション研修なども繰り返し実施し ながら、新しい意見を取り入れる企業風土の醸成にも注力 します。すべての企業活動は人間が行っていることであり、 冒頭に述べた人権を尊重しながら、コミュニケーションを 通じた相互理解を深めていくことが重要です。
もう一つ重要なのが、「安全」です。常に現場で仕事をし てきた私にとって、すべての基本は「安全」にあると考えて います。それぞれの現場で取り組んでいるカイゼン活動は、 コスト抑制が第一の目的ではありますが、同時に忘れてな らないのが教育です。安全は、災害「ゼロ」が目標であり、「1」 や「2」もあってはなりません。「ゼロ」にするために、あらゆ る側面から教育・訓練をし続けていくことが重要であり、そ れは従業員に限らずトップやマネジメント層も同様です。
そして、常にレビューを行い、監査などのチェック体制も含 めて省みることを安全活動の基本として実施していきます。
ガバナンスに関しては、取締役会を中心に、より効率的か つ実践的な形で運営できるよう、力を入れていきます。取締 役会に関しては、毎年、実効性評価を実施していますが、今 後は、社外取締役も交えて、より具体的な事業戦略について、 さらに深い議論ができるように改善していきます。社外取 締役の方々との意見交換の機会も、これまでの月1回の取締 役会にとどめるのではなく、取締役会前に実施する経営戦 略会議(業務執行会議)にもオブザーバーとして陪席いただ き、細かい事業動向を共有し、業績回復に向けた具体的なご 意見・ご提言をいただけるようにしていきます。また、取締 役会の運営方法についても、上程する議案からすべて見直し、 報告事項に割く時間を減らし、より事業戦略についての議 論ができるよう工夫していきます。
2025年度の事業環境見通しと 中計2年目の主要な施策について
2025年度については、これまで以上に変革を加速し、構 造改革を推進することを方針に掲げています。無線・通信 事業の構造改革を断行しながら、マイクロデバイス事業の ビジネスポートフォリオについても抜本的な見直しを図り、 マテリアル事業については方針を決定していきます。
その上で業績については、注力領域である無線・通信事業 の成長と、マイクロデバイス事業の黒字化により、増収増益 を見込みます。
無線・通信事業は、災害の激甚化を受けて水・河川管理予 算や防災情報システム需要等が増加傾向にあることに加え、 防衛事業の拡大から、ソリューション・特機事業の受注が増 えると見込んでいます。
一方で、マイクロデバイス事業については、市況などの 不安要素を完全には拭いきれていません。特に米中での輸 出規制がかかる中、最先端の半導体についても製造能力を 高めてきた中国の動きは大きなリスク要因と見ており、さ らには米国の関税動向により、これまでの半導体業界での セオリーが崩れていく可能性もありうると見ています。当 社としては、原価低減の取り組みを続けながら、下期以降の 市況回復を見据え、黒字化を果たしていきます。
資本コストや株価を意識した経営について
当社のPBR が低水準で推移していることについては、経 営上の重要課題と認識しています。これを克服するためには、 最優先課題は業績の回復しかありません。業績を回復させ るためには、まずは経営の設計図を示し、それに従って活動 していくことが重要です。 現時点での当社の中期経営計画の目標値が資本市場の皆 様からの期待値に届いていないことは認識していますが、 まずは最低限でもその目標値を達成すること。そして、構 造改革などの経営の設計図をしっかりとお示しし、その上で、 その設計図の確からしさを証明する術として、一つひとつ 結果を見せていくことが肝要です。 これらをしっかり実行し、業績数値として示せるように なれば、資本市場の皆様からの期待にもお応えできるので はないかと考えます。 一方で、当社のコア事業である無線・通信事業についても、 その社会的な意義をまだ世の中に十分訴求しきれていない とも感じています。例えば、医療現場で使われる超音波診 断などは、無線技術がなければ実現せず、私たちの提供する 技術は目に見えないながらも大きく社会に貢献しています。 当社の事業が、世の中のどのような領域でどのように貢献 しているのか。そうしたことをわかりやすくご説明しながら、 新たな体制下で進めていく研究内容をはじめとする当社経 営の設計図を、早くお示ししたいと考えます。 株主還元については、株主の皆様への1株当たり配当金 は年間36円を下限とし、2026年度にかけて配当性向40% を目指す方向に変更はありません。成長投資を優先しつつ、 自己株式取得も機動的に実施する方針です。また、利益成 長を通じて、配当水準の向上も目指していきたいと考えて います。
ステークホルダーの皆様へ
日清紡グループは今、自らを変革する過渡期にあります。 村上前社長の体制下で実施した事業ポートフォリオの変革 で、売上構成は大きく変化しましたが、それでもまだ十分 変わりきれておらず、収益力を強化していくためにも、もっ と変えていかなければなりません。私はそのポテンシャル が日清紡グループにはあると確信しています。 私が今後お示ししていく設計図は、大改造になります。 設計図に沿って行動することで、収益力を伴いながら日清 紡グループの変革を実現していきます。また、ステークホ ルダーの皆様にとっても、当社の事業内容や目指す方向性、 さらには変革していく姿をわかりやすく業績回復を伴う形 でお示ししていきたいと考えています。 ステークホルダーの皆様には、引き続きご支援賜ります ようお願い申し上げます。