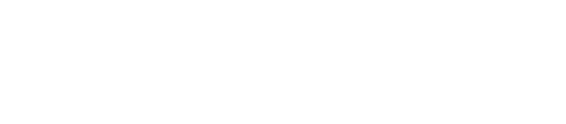- ホーム
- ニュースリリース
- お問い合わせ
-
グループ概要グループ概要 TOP
- トップメッセージ
-
会社概要
-
企業ビジョン
-
戦略的事業領域
- コーポレート・ガバナンス
- 事業ポートフォリオの変遷
-
事業概要
-
株主・投資家情報
-
サステナビリティサステナビリティ TOP
-
マネジメントメッセージ
-
サステナビリティ・マネジメント
-
環境・エネルギー分野の貢献
-
安心・安全な社会づくり
-
グローバル・コンプライアンス
-
サステナビリティ関連
データ - 編集方針
-
- 研究開発
- 採用情報
日清紡グループの財務戦略

取締役 常務執行役員
塚谷 修示
収益性向上を喫緊課題として進め、
事業ポートフォリオを変革して
企業価値の向上を図っていく
財務戦略の基本方針
日清紡グループは、中長期的な投資とリスクに備え、財務健全性を維持しながら収益性や効率性を重視した経営の推進を財務戦略の基本方針としています。
なかでも、収益性を高めることは喫緊の課題です。全セグメントで利益創出の努力を促していきます。大幅赤字を計上したマイクロデバイス事業はもちろんですが、それ以外に各セグメントの赤字を計上したサブセグメント事業をすべて黒字化するだけで50億円程度の増益効果になります。また、利益の出ている事業についても、さらにその収益性を高める努力をしていくことが重要です。また、効率性の観点から、装置型産業に比べて投資効率の高い組立型産業である無線・通信に力点を置いていきます。
財務健全性についてもその前提は利益の創出です。利益と減価償却費の範囲内でできるだけ負債の削減を進めていきます。それが中長期的な投資やリスクへの備えにつながると考えています。
当社の企業理念の根底には「企業公器」という考え方があります。「企業公器」は、社会に価値を提供することで利益を得るということであり、利益を生まない事業にしがみついていることは、「企業公器」の責務を果たしていないとも解釈できます。私は今一度、「企業公器」の意味を考えながら、その先の成長を見据えた事業ポートフォリオ変革を進めていきます。
2024年度の業績を踏まえて
2024年度は、ブレーキ事業子会社のTMD FrictionGroup の売却と(株)国際電気のグループ化で、装置産業の大きな塊がなくなり、組立型産業が充実した節目の1年でした。売上高はTMD が抜けたことで減収となりましたが、営業利益は国際電気のグループ化もあって増益、親会社株主に帰属する当期純利益も、前期に計上したTMD 売却に伴う特別損失がなくなったことで黒字回復を果たしました。一方で、セグメント別に見ると、市況の悪化でマイクロデバイス事業が赤字に転落した影響を、不動産の分譲事業で埋めた構図です。無線・通信事業の収益力を高めていかなければなりません。
また、総資産が前年度末から膨らんでいます。円安に伴う在外資産の評価額が増加した影響もありますが、ここでの課題は在庫です。電気部品の供給不安やサプライチェーンの混乱もあって、2024年度末は1,635億円とここ数年、高止まり状態でキャッシュ・フローを圧迫しています。売上の拡大と同時に、効率性の改善に向けて事業構造改革を加速していく必要があります。
事業ポートフォリオ変革
事業ポートフォリオ変革については、取締役会でも議論を深めています。当社は繊維から無線・通信まで幅広い事業を展開するコングロマリットですが、その一つひとつの事業環境や戦略が異なる中で、社外取締役も含めた取締役会のメンバーが理解を深めながら議論を進めていくプロセスは、説明する側も理解する側もかなりの労力を必要とします。2025年からは社外取締役向けに、各セグメントから直接ブリーフィングをする機会を設けるなど、工夫もしています。ホールディングスには特に、重要な経営判断が委ねられますし、その重要な意思決定についてスピード感も求められます。果断な経営判断をスピーディにしていくという点で、コングロマリット・ディスカウントの要素を感じることもあります。
個々の事業については、WACC(加重平均資本コスト)やROIC などを活用して、資本コストを意識した経営管理を進めてきました。各セグメントでROICの推移を把握できるようになり、今後もその推移を追っていくことが大切になると思います。コングロマリットゆえに、全社レベルで統一したWACC やROIC を適用できない点はもどかしさも感じますが、2024年度は金利が上昇したことも加味すると、グループ全体のWACC は中期経営計画で開示した5.7% から上昇し、6%を超えてきていると認識しています。事業によっては、ROIC ツリーに落とし込み、社員への理解・浸透を図れているところも出てきています。
事業ポートフォリオ変革を進めていく上では、ROIC 経営を通じて設定したハードルレートに達しているかどうかといった定量的な分析もしますが、その事業が立ち直るかどうかは、技術を含めた競争力です。事業戦略の肝は競争力にありますから、CFOとしては、事業がそれぞれの競争環境においてどのように競合と戦い、どのような時間軸でどのようなリソースを投下していくのか、それに基づく売上計画や利益計画になっているのかを注視しています。その上で、その事業が日清紡グループ内にとどまるべきかどうかというのはまた別の判断になります。日清紡グループの傘下にある以上は、グループ内でシナジーを創出していることが重要だと考えます。
事業ポートフォリオに関しては、しっかりと組立型産業である無線・通信の成長戦略を構築・遂行し、それと同時にマテリアル領域を中心に事業の整理を進め、装置産業の比率を減らしていく方向になると考えます。
キャピタルアロケーション
中期経営計画では、3年間の累積営業キャッシュ・フローと資産売却で、約2,900億円のキャッシュを創出することを前提に、そのうちの約1,900億円を設備投資と研究開発費に、約400億円を注力領域での戦略投資に振り向ける計画としていました。初年度の業績ではキャッシュの創出がふるわず、現時点で計画していた軌道から乖離が生じており、これについては、投資家の皆様から信任を得られるような現実的な目標へと修正する必要があると認識しています。
一方で、主としてM&Aを想定していた戦略投資に関しては、2024年度には金額は10億円と小ぶりですが、船舶が 川での自動航行を進めていく上で不可欠な技術を有する独ベンチャー企業のARGONICS GmbH を買収しました。将 来、オランダの日本無線(株)の子会社Alphatron MarineBeheer B.V.が有するレーダーと組み合わせ、川での自動航行を実現していきます。
株主還元に関しては、1株当たり36円の年間配当金の水準を下限とし、2026年度にかけて配当性向40%を目指します。また、有利子負債残高についても、2,000億円超の現水準は多すぎると考えており、削減していきたいと思います。
PBRの向上施策
PBRは依然、1倍割れの状況を解消しておらず、強い危機感を持っています。PBR に関しては、その構成要素である分母と分子の両方で改善に向けたアプローチをとっていきますが、何より重要なのは分子の収益対策です。ここは、不動産事業を除く利益の水準を倍増させないといけません。収益性が倍になってくれば、ROE10%は届かない目標ではありません。今は何より、有言実行で実績を示し続けることで、資本市場の皆様からの信任を得られるよう尽力していきます。
2035年近傍の営業利益率10%、ROE10%以上という達成に向けても、一丁目一番地は収益の改善です。成長事業 を見出して育成し、収益の向上を図る必要があります。また、これにはROA の観点も絡んでおり、現状6,800億円程度の総資産についても圧縮していかないと、結果としてROE10%の達成は難しいと考えています。収益をしっかり上げていく活動と同時に、在庫の削減や不要資産の整理を進め、不採算事業の整理についても聖域を設けず決断していくことが肝要です。
石井新社長と私を含む現役員らとは、2年くらい前からグループの抱える諸課題の認識・共有を図りながら、課題解消に向けた準備策を練ってきました。これまで以上にスピード感のある形でいよいよ実行フェーズに入っていきます。
非財務指標の開示充実
非財務指標に関しては、私が旗振り役となる形で、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワークに沿った開示プロジェクトを進めてきました。これまでの3年間で、すべてのセグメントで将来シナリオに基づくリスク・機会の分析が進み、2050年までのネット・ゼロ目標に向けて、2030年までにCO2 排出量を2014年比で半減させるという目標は射程距離に入っています。今は、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)について、どのような方針でセグメント展開していくかを検討しており、2026年度以降には全セグメントでTNFD開示に向けた活動を進めていきます。
サステナビリティの取り組みを強化していくことは、企業の レジリエンスを高めることにほかならないと思っています。この取り組みは、中長期的に資本コストの低減につながるという信念で進めています。
- 株主・投資家情報TOP
-
経営情報
-
コーポレート・ガバナンス
-
個人投資家の皆様へ
-
IRライブラリー
- 財務ハイライト
-
株式関連情報
-
IRニュース
-
その他IR情報
- IRサイトマップ