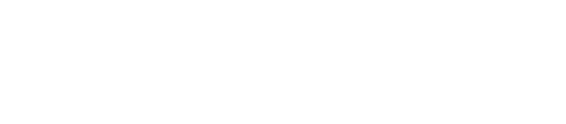経営戦略と両輪でサステナビリティ活動に取り組み、
社会課題の解決に貢献していく
経営戦略と両輪でサステナビリティ活動に取り組み、社会課題の解決に貢献していく
揺るぎない理念を堅持しながら、変えるべきところは変える
2025年4月から、経営戦略室長に着任した熊川哲也です。日清紡ホールディングスでは、経営戦略とサステナビリティ推進活動の企画実行の一元化を図るため、組織再編を行いました。経営戦略と両輪でサステナビリティへの取り組みを進めるべく、本質的な事項を見極めつつ、それぞれの機会とリスクに応じたメリハリのある対策を講じてまいります。活動の意義について社員をはじめとしたステークホルダーに理解、納得してもらいながら、日清紡らしいサステナビリティへと進化させていきます。
日清紡らしいサステナビリティとは何か。それは「企業公器」「至誠一貫」という、創立当初から伝わっている基本精神につながります。日清紡は社会課題に応じて事業ポートフォリオを変化させてきましたが、歴史の中で積み重ねてきた無形の資産「信頼」の源泉である基本精神は変わりません。この精神を基盤に置き、社会課題の解決に貢献していきます。その上で、もっとも重要なのは「人」です。日清紡では古くから「事業は人なり」という考えが根底にあります。会社は人で成り立っており、人財、つまり社員が企業にとって最も重要な価値創造の源であるという考え方です。私たち社員一人ひとりが、お客様や社会から寄せられる期待に応えようとする姿勢が、長い歴史の中で「信頼」の醸成に結びついてきたのです。
今、日清紡グループは更なるポートフォリオ変革を進めています。海外事業も多く、また近年、グループに加わった事業もあります。国民性も企業風土も異なるバックグラウンドを持つ社員に、トップマネジメントの考えを理解してもらうためには、時間をかけて諦めることなく対話を繰り返し、教育をし続けるほかにはないと考えています。揺るぎない理念を持ちながら、変えるべきところは変えていくこと。これがこの先も当社が生き残っていくために必要であると認識しています。今後も、求心力を持った新しい企業風土づくりに取り組んで行きます。
日清紡にとって、本質的な課題は何かを見極めて進める
サステナビリティに関わるすべての活動は、社会の風を感じつつも、企業経営の観点から何が本質的な課題であるのか、何に取り組むべきなのかを考え、日清紡としての意思を持って進めていきます。
一人ひとりの社員が「志」を持ち、会社の成長を自らの成長に重ねてもらう
私は、サステナビリティ活動の中で、特に重要な項目は「人財」だと思います。企業活動の全ては人が行うものです。良い人財が結集すれば必然的に他もついてくるだろうと考えています。
人財の多様性に関しては、他社で経験を積まれた方を積極的にキャリア採用することで、様々な場面で新たな知見を得ることが多くなっており、会社の成長のために欠かせない人財の確保に結びついています。第6期サステナビリティ推進計画(2025〜2027年度)ではキャリア採用の目標を引き上げ、管理職比率で20%以上を目指しています。女性管理職もまだ少ないながらも確実に増えてきています。新卒採用時点での女性比率は第5期サステナビリティ推進計画(2022〜2024年度)でほぼ計画通りとなっており、多様な働き方ができる環境も整ってきましたので、こちらもKPIを引き上げて更なる強化を進めます。
また、人財育成の面では、ラーニングマネジメントシステムの導入など入社後の教育・研修の環境整備が進み、社員自らの意思でさまざまなプログラムを受けることができるようになりました。昇給昇格の必要要件となるプログラムもあり、外部講習も取り入れるなど内容もハイレベルになっていると感じています。教育体系も日清紡グループとして合同で行っていますので、グループ会社各社間での横の交流もできつつあります。当社の事業ポートフォリオが大きく変革している中、新しい領域でも活躍できるようにリスキリング環境の整備に引き続き取り組んでいきます。
優秀な人財を惹きつけ、育てるには、会社と社員の「志」を積極的に伝え、魅力を上げていくことが重要であると考えています。一部の事業で、社員一人ひとりに「志」について考えてもらう機会を設けています。社員に仕事への「志」を持ってもらい、そしてそれが会社の「志」と共鳴できれば、大いに活躍し成長していただけるはずです。社員が「志」について考え、明確にできるような取り組みを今後も行っていきます。
次に環境分野についてですが、自社が事業活動による環境負荷を低減することは当然のことです。第5期サステナビリティ推進計画(2022~2024年度)の温室効果ガスの排出量削減は、すでに2014年度対比で55%削減(目標35%削減)を達成しました。これは、国内グループ各社で再生可能エネルギーの利用が進んでいる効果のほか、TMDグループの事業譲渡や、国際電気グループが新たに日清紡グループに加わったことなどの影響を加味したものです。今後も、カーボンニュートラルの達成に向けて更に高いKPIを設定し、しっかり取り組んでいきます。
一方、環境負荷の緩和に資する「持続可能な社会に貢献する製品の拡販」は、売上に占める割合を60%以上としていた目標に対して47%となっています。2024年度は未達成となってしまいましたが、ここはもっと比率を上げていくべきだと考えています。第6期サステナビリティ推進計画(2025~2027年度)では65%以上を目標に置き、柱の一つとして進めてまいります。
生物多様性保全、TNFDなど自然資本に対するリスクと機会の分析評価については、現在全体的な調査を進めており、大きな影響がある事項があれば対応を行っていく方針です。そのほかの環境に関する指標・目標はおおむね順調に推移しています。
多くのステークホルダーとともに進める、サステナビリティへの取り組み
全てのステークホルダーに関わる人権の尊重についてですが、国内外で実施している人権意識の啓発活動や研修は、これからも継続して行います。研修や教育を繰り返すことによって、ハラスメントやコンプライアンス違反の撲滅につなげていきます。人権デューデリジェンス活動も継続的に行っており、2025年度以降は本格的な人権リスク評価に取り組む予定です。
私たちは多くの取引先との協働によって事業を進めています。現在のような不確実性の高まるビジネス環境を鑑みると、外部環境の激変も視野に入れながら、サプライチェーンをより強くする施策を打っていく必要があると考えています。取引先の皆様から寄せられるご意見に真摯に耳を傾け、サプライチェーンを維持しながらも、不測の事態に備えて強靭化しておかなくてはなりません。さらに、私たちだけでは解決できない大きな課題についてはステークホルダーの皆様とも協力し、サステナブルな社会の構築の一翼を担える企業を目指してまいります。
私は、企業が社会での存在価値を認められることが、事業活動をしていく上で大切だと考えます。経営戦略とサステナビリティ活動を両輪で進めることで、企業価値を向上させていきます。これからも株主や社員をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応えながら、着実にサステナビリティ経営を進めてまいります。一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
日清紡ホールディングス株式会社
執行役員
熊川 哲也